
CM(コンストラクション・マネジメント)方式の概要
|
CM方式とは、
分離発注・設計・施工管理を建築主の代行としておこなう
建築主の代理人(コンストラクション・マネージャー:以下CMr)によって実施される方式。
全ての原点を
建築主におくことがCMをおこなう目的であり原点でもあります。
私どもと一緒に夢のある住宅を実現しましょう。
|
|
一括発注と分離発注の違い
|
|
| 一括発注 |
|
分離発注 |
|
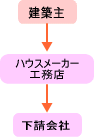 |
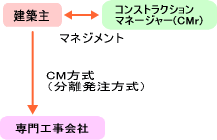 |
|
住宅のローコスト化や長持ちする住宅は皆さんの当然の欲求です。
また、住宅の性能は、建築主の意向を大きく反映させたいものです。
しかし、従来のやり方では、非効率的な面や具合が悪い面が多く存在します。
建築主の望むクォリティ、そして低コストを実現する手段の一つとして、CM方式(分離発注)を取り入れています。
▲TOP
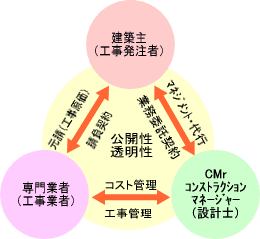 今までの発注方式は、工務店側の一方的な情報に頼ってました。 今までの発注方式は、工務店側の一方的な情報に頼ってました。
工務店側は建築主にたいして明らかにできないことが、生じていたというのも事実です。
広告宣伝費や営業経費等は、「建築主が負担しているの?」「下請け業者が負担しているの?」など不明瞭な諸経費。
「多重下請け構造ではないの?」など不明瞭な下請け業者。
今までの一括での発注方式では多くの??ゾーンが存在しました。※工務店側としてはやむを得ない事情もあります。
株式会社カク企画設計では、まずそのあたりをオープンにいたします
▲TOP
- 全ての業種が元請業者であり、各専門工事会社の工事明細がすべて建築主に公開されます。
あいまいさは通用しません。
「基礎工事で損したけん、仕上げで工事費ば穴埋めするバイ!」とか通用しません。(博多弁です)
- 一括請負による工務店の価格構成・配分の??ゾーンが無くなります。
- 求めるもの対して、価格配分を建築主の主導(好み)でおこなえます。
- 建築主と設計者によるオリジナルティを発揮できる。
- ローコスト化の手段としての成果が見込まれます。
- 建築主の積極的な参加は、管理の徹底にも結びつくことになるので手抜き工事や欠陥の防止につながります。
- ハウスメーカー等の会社側に縛られることなく、建築主の側に立った設計と管理がおこなえます。
| 設計施工一括発注方式とCMによる分離発注の比較 |
| 項目 |
設計施工一括発注 |
CMによる分離発注 |
| 建築主の立場 |
建築主は出来上がったものを受け取るという受動的な立場。反面、手間がかからない |
建築主は計画・設計・施工者選定・管理に積極的に参加。だけど時間はとられる。 |
| 設計者の立場 |
設計の内容は会社のマニュアル、仕様に沿っておこなわれることが多い。外注を活用することも多い。
コスト管理、工事管理には基本的に参加しない。 |
建築主とともに基本コンセプトや設計内容を常に話し合いながら進めていく。
設計のみならず、コスト管理、工事管理まで携わる。 |
| 専門工事会社の立場 |
下請けとなる。建築主や設計者と直接話し合う機会はほとんどない。 |
自社の施工部分に関して元請となる。建築主や設計者と直接話し合う機会が増える。 |
| 実務の形態 |
営業、設計、工事管理などの分業形態が多い。 |
分業はあまりおこなわれない。 |
| 契約の形態 |
設計、施工とも一括で請負契約を交わす。
まれに設計を分離することがある。 |
設計管理、施工者選定などのマネジメント業務は委託契約。工事は各専門工事会社と請負契約 |
| 必要経費 |
宣伝・営業費用、モデルハウスなどに多くの費用がかかる。 |
技術者中心なので、宣伝・営業に費用がほとんどかからない。 |
| 公開性・透明性 |
建築主に対して、基本的に原価などは非公開。 |
原価や施工状況などを常に建築主に公開しながら進める。 |
▲TOP
いいえ!そんなことはありません。何事にも表と裏があります。
CM方式とは、ある前提の上に成り立っています。
それは、われわれ設計士はもちろんのこと、建築主も積極的に新築住宅に参加しなければならないということです。
毎日が忙しい日本人にはここが最大のネックですし、また、現場の進行状況により軌道修正を余儀なくされる場合は、そのシステム性から時間を要する場合があります。(個人的にはリフォーム関して言えばCM方式は不向きだと思っております)
まず、そのあたりを理解していただいた上で、建築主とわれわれ設計士と専門工事業者と三者で協力し合い住宅をつくり上げていきます。
一括発注に比べ労力や責任が要求されますが、その見返りは素晴らしいものになるでしょう。
では、具体的な苦労(デメリット)とはどのようなことでしょうか。
▲TOP
建設会社やハウスメーカーは介在しないので、建築主が発注者であり、総合請負者でもあります。それには下記のような責任がともないます。
-
専門業者(職人)選定の責任
-
委託業務・発注業務に対する支払いの責任
-
リスク回避の責任(保険等への加入)
CM方式の場合、下請け業者は存在しません。
全ての専門業者と請負契約を交わす必要があります。
専門業者は必ずといってよいほど建設会社やハウスメーカーの組織に組み込まれており専門業者が建築主と契約を直接結び施工をおこなう風潮がないため、民間契約には注意が必要となります。
ざっと、並べてみましたがちょっと大変そうですネ。
その昔、新築住宅といえば、建築主が木材を調達し、職人に手間賃を払い工事を遂行していました(丼勘定という言葉も生まれましたが)。
今で言うところの、分離発注の形態ですネ、しかし、そこにはマネジメントといえるものが存在していませんでした。
建築主による直営工事をサポートし、または、代行などのマネジメントをおこなう。それが私ども建築の専門家としての設計者の役目です。
▲TOP
最終目的は直営工事の良さを最大限に発揮するために、設計事務所がマネジメントをおこなうことです。
受託した設計管理とマネジメント業務について、業務を遅滞なく誠実に実行する責任が負います。
契約や支払いといった、建築主でなければできないこと以外の大部分の業務は、設計事務所が建築主に代行しておこなうことになるでしょう。
- 資金計画とCM方式運行のアドバイス
- 業務マニュアル化による明確化
- 実務の代行
- 競争入札のシステムづくり
- 瑕疵担保責任のルール作成
- 各種申請業務
- 見積の分析
- 契約書の準備
- 設計
- 施工者の選定
- 建築主代理人としての工事監理者
- 工程表の作成
- 工事工程の調整
▲TOP
各専門工事会社は、通常の工事では下請けとして参加しています。ところが、分離発注の場合は元請です。
ここで、元請としての意識を切り替える必要があります。
元請は労災に対する責任を負います。政府労災は当然のこと、損害保険などでリスクをカバーできる業者が絶対条件となります。
- 労災・損害保険などへの加入
- 工事内容の改善案を建築主や設計者に提案
▲TOP
簡単ではございますが、CM方式(コンストラクション・マネジメント)を、ご理解いただけたでしょうか?
住宅に求められる性能は、昔も今もそうかわりません。
丈夫で長持ちし、快適で、美しさが求められているのではないでしょうか。
さらに、建築主の積極的な家づくりへの参加は、そこに満足度というファクターが加わることでしょう。
ご意見投稿
左欄のお問い合せメニューもご利用下さい。
|
|